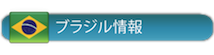
トピックス 2012年11月号
データでみるパラナ州のポテンシャル -在クリチバ日本国総領事館
ブラジル全州を見渡しても、幾つかの事項において相当の地位を有するパラナ州(州都クリチバ市)であるが、日本人一般にはサンパウロ州やリオデジャネイロ州ほどの知名度は得られていない。今月は知る人ぞ知るパラナ州の代表的なポテンシャルについて紹介する。
1 地理的特性
ブラジル南部3州の最北に位置し、同南部地域とブラジル国内その他の地域間の物流を陸路で行う際には、必ずパラナ州を通ることになる交通の要衝。また、国内最大の消費地であるサンパウロにも比較的近く、かつ他のメルコスール3国へのアクセスにも有利な立地にある。
同州主要港であるパラナグア港は、ブラジル第4位の輸出入取扱量を誇る。
なお、世界三大瀑布の一つとして有名な「イグアスの滝」と関連の諸施設は、パラナ州西部のアルゼンチン・パラグアイとの国境地帯に所在。
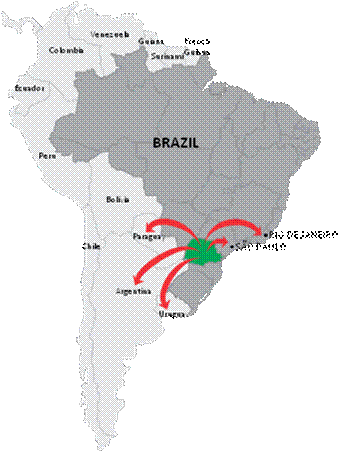
2 ブラジル有数の農業生産力
テーラ・ロッシャと呼ばれる肥沃な土壌が多く、早くから農業開発が進められた。
(収穫・生産高)
・第一位:トウモロコシ、フェイジョン豆、鶏肉
・第二位:大豆、小麦

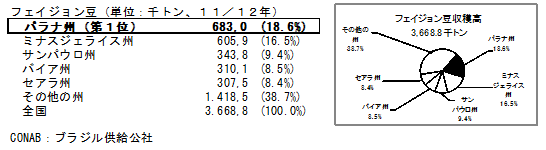
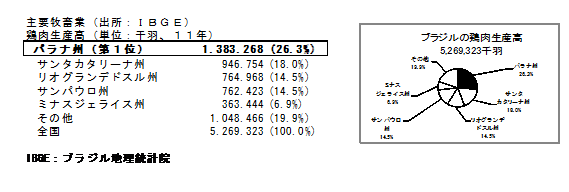
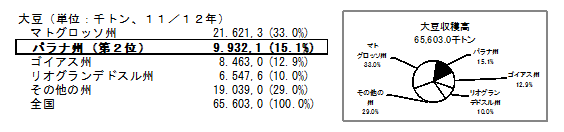
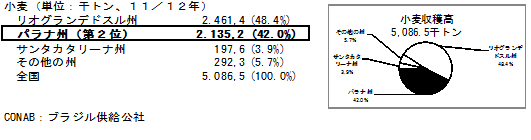
3 ブラジル第3位の自動車生産高
1995年以降税制優遇措置を導入して外国企業誘致等により工業化を推進した結果、自動車部門を主体にクリチバ首都圏を中心に外国自動車メーカーが相次いで進出し生産を拡大、それを支える関連産業も発展。
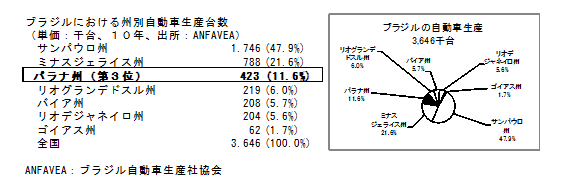
4 ブラジル第2位の日系人数
我が国とパラナ州との関係は、1930年代にサンパウロ州から日本人移住者が北パラナ等に入植した時に始まった。パラナ州には約15万人(北パラナ約10万人、クリチバ約4万5千人)の日系人が在住していると見られ、既に世代は五世までに達している。パラナ州の日系人は、現在も多くが農業に従事しているが、政治、経済、教育、医学、司法等の各分野でも大いに活躍している。また、同州から本邦への出稼ぎ者数は約7万人と見られている。パラナ州の日系人の評価は、誠実、勤勉等、非常に高く、おかげで我が国に対する評価も極めて親日的で、かつ日本語を解する質の良い労働力を提供できる素地がある。
5 豊富な電力エネルギー
地形的に河川に恵まれたパラナ州には、フォス・ド・イグアス市に世界第2位(中国の三峡発電所が世界最大)の14,000メガワット(MW)の発電能力を有するイタイプー水力発電所(パラグアイとの共同経営でブラジル側の権利は7,000MW、なお日本最大の黒川ダムは発電能力1,932MW)があるほか、パラナ州電力公社(COPEL)が州内に1,200MWを超える3つの水力発電所を含む19発電所(水力17、火力1及び風力1)で発電能力4,552.11MW(伯全体の発電能力の4.05%に相当)を有し、更に2ヶ所の発電所を建設中である。また、私企業等の発電能力は、約4,900MWであり、この結果、イタイプー発電所を含めた州内の発電総能力は約17,787MWと伯国内でも非常に電力に恵まれた州となっている。
上記は代表的な諸点を紹介したが、同州の利点等の詳細については、以下の公開サイトが参考となる。
課題
こうした利点が見られる同州であるが、残念ながらいわゆるブラジルコスト(複雑かつ高率の税制、各種公共サービスの非効率、労務管理コスト、物流インフラの不完全性等)はここでも存在し、同州内に既に進出した日本企業等もご苦労されている。在クリチバ日本国総領事館としては、在ブラジル日本国大使館及びパラナ日伯商工会議所と連携しつつ、出来る限りの支援を今後とも行っていく所存。
外交
1.パトリオッタ外務大臣のイスラエル訪問
- (1)パトリオッタ伯外務大臣は、10月12日から14日にかけ、中東においてイスラエルが置かれている困難な状況で唯一の解決策は対話による交渉であるとのルセーフ大統領のメッセージを伝える目的で、イスラエルを訪問した。
- (2)14日には、ペレス大統領を表敬し、イスラエルによるイラン核施設に対する攻撃の脅威に懸念を示し、イスラエルによる脅しや将来的な行動は、中東の安定を危険にさらすと忠告した。これに対し、ペレス大統領は、イラン制裁は核開発プログラムに効果を及ぼしておらず、軍事的行動をとる選択肢につき、準備ができており、真剣に検討されている旨返答した。
- (3)伯外務省報道官は、イランとの関係について、現段階では、ブラジルの立場に変更はなく、イランに対するいかなる軍事攻撃及び中東地域におけるいかなる軍事介入にも反対であると述べた。他方、ペレス大統領は、イラン核開発プログラムは平和的な目的を有しておらず、同問題に関し、米国のように単純であってはならないと断言し、最大の同盟国である米国を明らかに批判しつつ、イラン核開発の脅威は、中東地域全体に陰を落としていると指摘した。
2.パトリオッタ外務大臣の訪米
- (1)24日、第4回伯米グローバル・パートナーシップ対話出席のため訪米したパトリオッタ大臣は、クリントン国務長官と会談した。同会談において、クリントン長官は、伯はシリアの紛争解決にとり、非常に重要である旨述べ、会談後の記者会見でも、シリアで停戦を実現させ、体制移行を支援するための努力に伯が参加することを歓迎する旨表明し、米国がシリアの和平プロセスに関して伯の関与を歓迎する旨を明らかにした。クリントン長官は、米国は、訓練等を通じて、反体制派を支援してきていると述べたことに対し、パトリオッタ外相は、交渉による解決に向けた外交努力の強化を主張し、また、そのプロセスにおけるIBSAの重要性を強調するにとどまった。
- (2)また、同日、ナポリターノ国土安全保障長官と会談した際、同長官は、パトリオッタ大臣に対し、米国が査免のために要求している基準に照らし合わせ、ブラジルは「安全」な水準に達している旨伝えた。パトリオッタ大臣は、査免に向けての動きは進展しているものの、短期間での締結はないだろうと冷静に受け止めている。
 エルサレムの大統領官邸におけるペレス大統領との会談(写真:Avi Dodi)
エルサレムの大統領官邸におけるペレス大統領との会談(写真:Avi Dodi)

ワシントンにおける、ヒラリー米国務長官との共同記者会見(写真:State Department)
内政
2012年市長等選挙
10月7日及び28日、ブラジルの全国市長及び市議会議員選挙が実施された。
- (1)7日の第1回投票は、当国5,568市において実施され、市長選については、5,518市の市長の当選が確定した。市の設置されていない連邦区を除く26州都については、9州都の市長が有効投票数の過半数以上を獲得して当選した。当選した市長は来年1月1日に就任し、任期は4年間。
- (2)有権者数20万人以上の都市のうち、7日の投票で過半数を獲得した候補がいなかった50市(17州都を含む)では、28日に決選投票が行われた。
- (3)特に注目されたサンパウロ市長選は、第1回投票において、選挙戦をリードしていたPRB(ブラジル共和党)のルッソマーノ候補が第1回投票で落選し、決選投票はPT(労働者党)のアダッジ候補とPSDB(ブラジル社会民主党)のセーラ候補の一騎打ちとなったが、最終的に、アダッジ候補が勝利した。選挙キャンペーン当初に6%程度の支持率しかなかった同候補が当選を果たしたことで、同候補を個人的に推薦したルーラ前大統領の影響力が改めて浮き彫りになった。また、同候補の応援に貢献したルセーフ大統領の党内評価も上昇した。
- (4)また、今回の選挙で注目されたのは、PSB(ブラジル社会党)及び同党党首のエドゥアルド・カンポス・ペルナンブコ州知事である。PSBは、2008年選挙の市長当選者数と比べ40%以上の伸びを見せた。また、カンポス州知事は、レシフェ、ベロオリゾンテ、フォルタレーザ等市長選で自ら擁立した候補を当選させたことで、今回の選挙の勝者として注目を浴び、2014年の大統領選への出馬も噂され始めている。
- (5)野党については、PSDB、DEM(民主党)ともに大きく市長数を減らし、特にDEMは前回の2008年選挙から44%以上縮小した。PSDBは、サンパウロを始め決選投票での対PT対決ですべて敗れるなど敗北感がぬぐえないが、PSDB内においては、敗北したセーラ候補の影響力がPSDB内で下がったことで、ネーヴェス上院議員(前ミナスジェライス州知事)の影響力が増大し、2014年大統領選出馬の可能性が高まった。

アダッジ次期サンパウロ市長のルセーフ大統領表敬 (写真: Roberto Stuckert Filho/PR)
メンサロン事件公判
- (1)8月2日から開始されているメンサロン公判は、連邦最高裁(STF)において、既に、連邦議員による収賄や資金洗浄等の審理を終え、10月3日から、メンサロン事件の核心であるPT幹部による連邦議員の贈賄についての審理が行われていたが、9日、ルーラ前大統領の右腕とされたジルセウ元文官長及びジェノイーノ元PT党首らの有罪が確定した。22日にはすべての評決が終了し、被告37名の内、25名の有罪が確定した。24日から各被告に対する量刑の審議が開始されている。
- (2)有罪判決を受けた被告のうち、24日、マルコス・ヴァレリオ元広告代理店社長の量刑審議が終了し、約40年1ヶ月の禁固刑及び罰金刑が言い渡された。他の被告についての量刑審議は、11月7日から再開される見通し。
森林法改正
1.概要
森林法改正をめぐっては、本年5月、ルセーフ大統領は、同改正法案のうち農牧業推進に有利な内容の条項(計12条)につき拒否権を行使し、計32条を追加・修正する暫定措置令(以下「MP」)を制定した(※)ところ、MPの法律化に向け、連邦議会での審議が行われてきた。((※)本年6月号大使館情報参照)
その後、9月25日、連邦議会は、MPの一部を農牧業推進に有利となる内容に再度修正した上で法律化を承認し、大統領による裁可に付されたところ、10月17日、大統領は、右修正MPの一部につき拒否権を行使するとともに、MPではなく大統領令を制定することで、拒否権行使により生じた森林法の欠落条項を穴埋めするとの対応をとった。
2.大統領が拒否権を行使した主なポイント
(1)中規模及び大規模農牧場主が行うべき河岸植生回復義務の最低面積(河岸からの幅)を、当初のMPと比較して5m緩和する。また、大規模農牧場主が行うべき河岸植生回復の面積(河岸からの幅)の算定を州政府が行うこととする。
(2)河岸植生回復を行うにあたり、外来果樹やユーカリ等の単一栽培を認めることとする。
(3)乾期に水流がなくなる川幅2mまでの涸れ川について、農牧場の規模に関わらず、河岸から最低5m幅の植生回復義務を課す。
3.新たに制定された大統領令の主なポイント
(1)農地環境登録システムの規定
農牧地の環境情報を電子上で一元的に管理する「農地環境登録システム」を規定し、ブラジル全土の農牧地における環境の状況を把握する。
(2)環境規制プログラムの規定
上記システムに登録された農牧地の環境情報をもとに、森林法の実施を推進するための「環境規制プログラム」を規定。違法状態にある森林伐採地への植生回復義務については、以下のとおり規定。
ア 農牧場の規模に応じた植生回復義務の面積(河岸からの幅)を規定。
イ 河岸植生回復を行うに際しては、在来種を含むこととし、植生回復地における外来種の割合は50%を超えないこととする。
4.今次決定の影響等
(1)今回の大統領による一連の決定は、違法伐採者への特赦は認めない、違法森林伐採を助長しない、社会的な公正性を確保する、といった伯政府が掲げる基本姿勢を貫いた結果と言える。一方で、今次決定は、森林伐採地の植生回復義務の緩和等を目的にMPを修正した連邦議会の意思を無視するにとどまらず、議会での更なる紛糾を避けるため、拒否権行使により生じた森林法の欠落条項の穴埋めを、議会承認を経る必要のない大統領令で規定するものであった。(2)このため、農牧業推進派の連邦議員からは政府に対する反発や不信の声も聞かれているほか、新大統領令そのものの違憲性を疑う声も噴出するなど、今後の政権運営への新たな火種となる可能性も否定できない。
(2)今後、政府は、新たに制定した大統領令の合憲性を証明するのみならず、「農地環境登録システム」や「環境規制プログラム」の詳細規定に向けては、農牧業推進派・環境推進派を問わず幅広く意見を集約し、合意形成を推進していく必要がある。
Copyright © 2012 - Embaixada do Japão - Todos os direitos reservados

