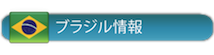
トピックス 2012年1月
- 気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)及び京都議定書第7回締約国会合(CMP7)について
- 日・ブラジル社会保障協定の締結
- 外交
- 内政
- サンタカタリーナ州ブラジル・日本親善週間-初めてブラジルの地を踏んだ日本人―若宮丸漂流民―
気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)及び京都議定書第7回締約国会合(CMP7)について
1 全体概要
2011年11月28日(月)から12月10日(土)にかけ、南アフリカ共和国ダーバンにおいて、気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)及び京都議定書第7回締約国会合(CMP7)が開催された。日本からは細野環境大臣、中野外務大臣政務官等が出席した。
2 今次会合における成果
今次会合における主たる成果は以下の3点。
- 将来の枠組みへの道筋
法的文書を作成するための特別作業部会を立ち上げ、可能な限り早く、遅くとも2015年中に作業を終えて、議定書、法的文書または法的効力を有する合意成果を2020年から発効させ、実施に移すとの道筋に合意。
- 京都議定書第二約束期間の改正案
京都議定書については、第二約束期間の設定に向けた合意が採択。我が国を含むいくつかの国は第二約束期間には参加しないことを明らかにし、その旨成果文書にも反映。
- カンクン合意実施のための一連の決定
COP16で採択されたカンクン合意に基づき、緑の気候基金の基本設計に合意。また、削減目標・行動推進のための仕組み、MRV(測定・報告・検証)の仕組みのガイドライン等、適応委員会の機能、国別適応計画の内容、資金に関する常設委員会の機能、気候技術センター・ネットワークの役割、対応措置やキャパシティ・ビルディングのフォーラムの立ち上げ等にも合意。さらに、新たな市場メカニズムについては、国連が管理を行うメカニズムの方法・手続の開発、及び各国の国情に応じた様々な手法の実施に向けて検討を進めていくことで合意。
3 今次会合における我が国代表団の対応
- 我が国政府は、COP16で採択されたカンクン合意を踏まえ、すべての主要排出国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みを構築する新しい一つの包括的な法的文書の早急な採択という最終目標に向けた道筋を今次会合で明らかにし、必要な作業に着手することで一致することを目指して交渉に臨んだ。
- 交渉の最大の焦点であった2013年以降の枠組みの在り方については、新たな作業部会を設置することなどの建設的な提案を行って交渉の進展に貢献した。他方、途上国が求めていた京都議定書の第二約束期間については、将来の包括的な枠組みの構築に資さないため日本は参加しないとの立場を貫いた。
- 細野環境大臣による演説等を通じ、上記の交渉立場に加え、東日本大震災という国難にあっても日本国民は気候変動問題に積極的に取り組んでいること、また、現在新しいエネルギーベストミックス戦略・計画に向けた検討と今後の温暖化対策の検討を表裏一体で進めていることを説明した。また、地球温暖化対策への効果的な取組として「世界低炭素成長ビジョン-日本の提言」を公表し、日本が約束した官民合わせて150億ドルの短期資金を今後も着実に実施していくことも表明した。
4 次回会合(COP18)はカタール・ドーハで開催される。

COP17閣僚級会合でステートメントを行う細野環境大臣
環境省(日本)提供
日・ブラジル社会保障協定の締結
1 昨年12月7日、東京において、日本側の加藤敏幸外務大臣政務官とブラジル側のマルコス・ガウヴォン駐日ブラジル大使との間で「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(日・ブラジル社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われた。この協定は、昨年5月に日本の国会で、9月にブラジルの連邦議会でそれぞれ承認されており、今回の公文交換を経て、本年3月1日に発効することになる。
2 これまでは、互いの国に派遣される被雇用者は日本とブラジル両国の年金制度への加入が義務づけられていたため、年金保険料の二重払いが生じていたが、今回の協定により派遣期間が5年以内の一時派遣被雇用者は、原則として派遣元国の年金制度の加入することになる他、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなった。
3 本件社会保障協定の締結により、企業及び企業駐在員等の年金保険料負担が軽減され、両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。
4 なお、今回の発行に向け、以下の日程で当国在住の説明会が実施される予定。
(詳細については各関係総領事館にお問い合わせください)
2月7日(火) マナウス
2月9日(木) リオデジャネイロ
2月10日(金)・11日(土) サンパウロ
2月13日(月) クリチバ
外交
12月15日から17日の日程で、フランスのフランソワ・フィヨン首相がブラジルを公式訪問し、15日、ブラジリアにおいてルセーフ大統領と会談した。この会談では、IMF改革、二国間の軍事協力などについて意見交換がなされ、また同日、ブラジル人留学生受入れのための協定や社会保障協定など4つの協定に署名がされた。
内政
1.世論調査
17日、ルセーフ政権に関する世論調査結果が発表された。この調査によると、ルセーフ大統領就任1年目における政権への評価は、良い/非常に良いが56%と、ルーラ政権同時期(41%)及びカルドーゾ政権の同時期(43%)の結果を上回った。
2.省庁改変及び内閣改造
本年初頭予定と報道されている内閣の改造予定について、ルセーフ大統領は大幅な改変や、省庁の合併についても否定しているが、報道では現在の38閣僚のうち約10閣僚が交代すると見られている。この交代人数は省庁の統合や大臣の健康状態により変動する可能性が高いが、少なくともサンパウロ市長選出馬が確実視されるアダッジ教育大臣の辞任に伴い、既に後任としてメルカダンテ科学技術省大臣が後任の教育大臣に就任することが確実視されている。
サンタカタリーナ州ブラジル・日本親善週間-初めてブラジルの地を踏んだ日本人―若宮丸漂流民―
2011年12月16日、サンタカタリーナ州フロリアノポリス州議会にて、サンタカタリーナ州ブラジル・日本親善週間開会式が開催され、山口在クリチバ総領事が出席した。当週間は、1803年に、4人の日本人が日本人として初めて世界一周をし、初めてブラジルの地を踏んだ史実を記念して、アンジェラ・アルビーノ・サンタカタリーナ州議会議員(PC do B)が報告者となり制定された、2010年11月22日付州法第15.324号に基づいて実施されたもの。
1793年、江戸に向かっていた宮城県石巻出身の漁師達は、塩屋崎沖(いわき市)で暴風雨に遭い遭難し、アリューシャン列島にたどり着いた後、イルクーツクでの7年間の生活を経て、当時日本との貿易や交流を推進しようとしていたロシア皇帝アレクサンドル一世の意向により、当時の首都であるサンクトペテルブルグに上京、皇帝に謁見した後に、遣日使節として皇帝の親書を携えたレザノフ使節団長(アダム・ラクスマンに続く第二次遣日使節)やクルーゼンシュテルン(ロシア海軍提督であり探検家)とともに、ロシア初の世界一周周航船ナジェーダ号で長崎に送り返されることになった。 彼らは、サンクトペテルブルグ近郊の港を出発したのち、コペンハーゲン(デンマーク)そしてファルマス(イギリス)、リオデジャネイロ沖(カーボ・フリオ)を航海し、サンタカタリーナ島(フロリアノポリス市)に1803年12月22日に到着、2か月ほど滞在した。サンタカタリーナ島での滞在に関し、クルーゼンシュテルンによる記録や、後に、仙台藩主の命令により大槻玄沢が漂流民より聴取してまとめた『環海異聞』には、ジョアキン・クラド・行政区(カピタニア)総督がレザノフ使節団長一行を歓待してレザノフ使節団長を総督邸に住まわせたり、一行が熱帯の動植物観賞やクリスマスから年末にかけての奴隷の習慣(お祭り)等を楽しんだ様子など多くのエピソードが記載されている。サンタカタリーナ島を後にした後、ナジェーダ号は、ヌクヴィア島(南太平洋・マルケサス諸島)などの港に寄り、約1年かけてカムチャッカ半島のペトロパブロフスク港に到着し、漂流民は1804年9月、石巻を出港してからようやく11年後に長崎に送還された。しかし、当時の鎖国政策により、ロシア船は入港すらできず、また漂流民も江戸での厳格な取り調べを受け、なかなか故郷に帰ることができなかったなど、漂流民の多くは不遇な晩年を送った。
以上の史実は、仙台藩主の命令により大槻玄沢が漂流民より聴取してまとめた『環海異聞』に記録され、現在では日本初の世界一周見聞録として知られている。この史実は日本、ロシア、そしてブラジル等各国の研究者の関心をひき、2003年には在ポルトアレグレ総領事館が『環海異聞』のポルトガル語訳を作成し、2011年、ブラジル・サンタカタリーナ州においても研究グループ『若宮丸サンタカタリーナ島協会』が発足した。現在、右協会は日本の『石巻若宮丸漂流民の会』とも活発に交流しつつ研究活動を行っており、今回の州法成立及び文化イベント開催に対しても多大な貢献をしている。
サンタカタリーナ州ブラジル・日本親善週間は、2010年12月16日から22日まで、サンタカタリーナ州議会、若宮丸・サンタカタリーナ島協会、ニッポカタリネンセ、ニッポ・クルトゥーラ等を始めとする当地日系諸団体が主催して開催され、延べ約350人が参加し、大盛況に終わった。2011年12月16日に州議会で開催された開会式には、アンジェラ・アルビーノ州議会議員、山口在クリチバ総領事、マリオ・サトウ・サンタカタリーナ日系協会連合会会長、ラファエル・コジオ・ノブレ・若宮丸サンタカタリーナ島協会会長等が出席し、スピーチが行われると共に、石巻若宮丸漂流民の会の理事であり、石巻市の住民として東日本大震災で被災された本間英一氏より寄せられた、東日本大震災の経験に関するメッセージも披露された。17日から22日には、カタリネンセ学校博物館にて、剣道、折り紙や漫画等のワークショップが開催され、クリスマス前にも拘わらず多くの参加者を得た他、22日にはフロリアノポリス史上初の灯籠流しがラゴア・ダ・コンセイサン湖畔で開催され、石巻市を始めとする東日本大震災の被災者に対する追悼の意を込めて、総勢約50人が灯籠を放った。
今回の親善週間を通じて、日系人が比較的少ない当地において、日本の歴史や文化、さらには住民にあまり知られていない当地の歴史に対する関心が強まったと共に、当地と石巻市との歴史的なつながりが広く知られるところとなった結果、東日本大震災の被災者に対する支援や被災地との交流への関心が更に高まっており、在クリチバ総領事館としては引き続きそれらの団体活動の仲介やバックアップを行っていきたいと考えている。

山口在クリチバ総領事の挨拶
右から:ルイス・中山 ニッポ・カタリネンセ協会会長、本官、アンジェラ・アルビーノ州議員マリオ・佐藤 FANSC会長ラファエル・コジイオ 若 宮丸・イーリャデサンタカタリーナ協会会長
Copyright © 2012 - Embaixada do Japão - Todos os direitos reservados

