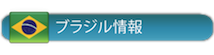
ブラジル便り2012年7月号
ブラジルの道路について
ブラジルの国際競争力の弱さや、今後のブラジルの持続的成長を阻害する要因として、しばしば「ブラジル・コスト」という言葉を耳にする。不十分なインフラストラクチャー、GDPの36%にも達するとされる高い租税負担、各種の労働保護政策がもたらす労働市場の硬直性などである。最近ではかなり引き下げされてきが、国際的水準からみれば依然として高い利子率も高コストの一因である。さらに付け加えると、労働生産性の伸びを上回る賃金コストの上昇や、技能労働者不足も重要な「ブラジル・コスト」の一因となりつつある。

今回はブラジルの道路事情について述べたい。写真はブラジリアの日本大使館のすぐ近くの道路を写したものである。みごとといえるほど大きな穴ぼこがいくつか道路の真ん中にあり、私が赴任した4月から今日までほったらかしである。ご存知のように、大使館地区は広々とした空き地のなかに各国の大使館が点在していることから、この近辺の車のスピードはかなり速い。万一これを見逃せば、パンクするか、大きな事故となりかねない。実際、大使館員の1人は自慢の愛車をパンクさせている。
ブラジルでは歴史的に鉄道が沿岸部を中心に発達したため、必然的に道路輸送に大きく依存しており、ブラジルでの貨物輸送は道路輸送が約58%を占め、鉄道が25%、水路が13%、パイプラインが3.6%、航空が0.4%となっている(Ministério dos Transportes, Aunários Estatísticos)。したがって、輸送コストは道路輸送の効率性に大きく左右される構造となっている。ブラジルの道路の総延長距離は2007 年には164 万km に達したが、舗装率は低く、全体で12.9%に過ぎない。因みに、インド、中国のそれは、同時期にそれぞれ66%、47%である(世界銀行のデータ)。ブラジルでは高速道路に相当する長距離路線の国道はホドビーア(rodovia)と呼ばれ、07 年には74940km が整備されていたが、国道であっても全てが舗装されているわけではなく、まだ8 割に過ぎない。もちろん、写真のように、舗装がなされていたとしても補修が追いつかず、劣悪な状況であるため輸送コストは大きく跳ね上がる。例えば大豆の話であるが、内陸から沿岸部まで運ぶ途中で、道路状況が悪いことから、かなりの割合の大豆が荷台からこぼれ落ちるともいわれている。世界経済フォーラムの「グローバル競争レポート:2011-2012」では、ブラジルの道路の質は142カ国中118位である。
他方、こうした道路整備状況の下で始まった急激なブラジルのモータリゼーションは、サンパウロ、リオデジャネイロなどの大都市では深刻な交通渋滞をもたらしている。大サンパウロ圏では車の数が2003 年以来毎年7.5%の率で増加し、日々1000台の割合で増えているとされる。TIME 誌ではかつてサンパウロの交通事情を「世界最悪の交通渋滞」と紹介したが、人々は車やバスの通勤に長時間を費やしている。09 年7 月10 日には記録的な渋滞となり、市交通局でモニターしている835km の道路のうち293km で渋滞が生じた。サンパウロ市では97 年からナンバー・プレートによる市中への乗り入れ制限(ホジージオ)を実施しているが、市内の地下鉄網やバス輸送が不十分なことも交通渋滞の要因である。
PAC(経済成長加速計画)での進展も遅れていることを考慮すると、ブラジルの道路設備の改善にはかなり時間がかかりそうである。私が通勤している道路の補修はいつのことになるのであろうか。
Copyright © 2012 - Embaixada do Japão - Todos os direitos reservados

