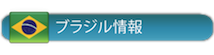
最近の経済情勢 2013年09月
1.経済情勢・経済見通し
(1)中銀が週次で発表している市場(エコノミスト調査)の経済成長予測に関し、8月30日の発表では本年の経済成長見通しは2.32%と前週(2.20%)より若干上昇したものの、明年の成長見通しは2.30%と前週(2.40%)の見通しから下降した。
(2)8月30日、ブラジル地理統計院(IBGE)は、本年第2四半期のGDP統計が、前期比1.6%、前年同期比3.3%の伸びを記録した旨発表した。最大の伸びは、農業(3.3%)であり、次いで製造業(2.0%)、サービス業(0.8%)となっている。前年同期比では農業(13.0%)、製造業(2.8%)、サービス業(2.4%)の順になっており、市場の予測を上回る結果となった。
2.経済政策等
(1)8月1日、マンテガ財務大臣は、昨年10月1日より実施されている100品目の輸入関税引上げ措置について、1年間の引上げ期間が切れる本年9月30日を以て終了し、引上げ前の関税率に戻す旨発表。
(2)8月12日、ボルジェス運輸大臣は、記者会見において、本件入札の締切期日を最低1年間延期すると発表し、その後、同15日、伯国家陸運庁(ANTT)は、公示にて、本件入札のスケジュールを無期限に(sine die)延期する旨発表。
(3)8月21日、ルセーフ大統領は、ドル高に対する対応策を検討するため、関係閣僚及びトンビーニ中銀総裁を招集。同日、マンテガ財務大臣、ベルキオール企画予算大臣及びトンビーニ中銀総裁による緊急の国家通貨審議会(CMN)が開催され、翌22日、総額600億ドルに上る為替介入を年末まで継続することを発表。
(4)8月26日、マンテガ財務大臣は、米国の連邦準備理事会(FRB)がわかりにくいメッセージを送り世界の市場を混乱させたため、ブラジル経済は小さな危機(mini crise)に見舞われていると発言。
3.中銀の金融政策
(1)8月21日、トンビーニ総裁は、ドル高傾向の金融市場を注視するとともに、緊急開催された国家通貨審議会(CMN)に出席するため、米国訪問をキャンセルし、翌22日、総額600億ドルに上る為替介入を年末まで継続することを発表。
(2)8月29日、中銀の金融政策委員会は、以下の声明を発表し、政策金利(Selic)を、前回(7月10日)に引き続き0.50%引き上げ、9.0%とすることを全会一致で決定。
(ア)金融政策委員会は、政策金利の調整の継続として、バイアスなく、政策金利を年9.00%に引き上げることを全会一致で決定した。
(イ)金融政策委員会は、この決定が、インフレ率を低下させ、その傾向が明年も持続することに寄与するものと理解している。
4.為替市場・株式市場
(1)為替市場
(ア)8月のレアル為替相場は、米国の金融緩和政策の解除への期待を主要因として、レアル安が進行する流れとなった。8月初旬は、7月までの貿易赤字が過去最大に達したこと等から、レアル安が加速した後、米国の雇用統計の悪化や中銀の為替介入によりドルは一旦下落。しかし、ブラジル企業の外国送金によるドル買いの影響等から再びドルが上昇。その後も中銀の介入を警戒しながらも、米国の金融緩和策の解除を見越してドルが買われる展開となった。
(イ)その後、中銀の為替介入にも関わらず、米国の金融緩和政策の解除の見通しが更に強まったこと、中国の経済成長の減速、一次産品価格の下落によりブラジル経済自体低迷していることの見方からレアルが弱含み、18日には一日のドルの上げ幅としては2011年11月以来となる2.09%ものドル上昇を記録した。
(ウ)更に20日、マンテガ財務相が、「現在の為替水準はブラジルの製造業の競争力を高める。」と発言したことが、レアル安を容認するものと受け止められ、中銀による36億ドルに上る為替介入などが行われたものの、ドルは引き続き上昇。21日には、公開された米国の連邦準備制度理事会の議事録で金融緩和政策の変更を支持する意見が多かったこともあり、本年の最安値となる1ドル=2.4457レアル(売値)を記録した。
(エ)22日、政府・中銀は、急激なドル高レアル安の進行に対処するため、総額600億ドルに上る為替介入を年末まで継続することを発表した。このような政府の為替対策の効果により、翌23日には、それまでの急激なドル高レアル安の流れにひとまず歯止めがかかることとなり、月末は1ドル=2.3725レアル(売値)で取引を終えた。それでも月末のレベルは、前月末比で3.59%下落しており、4カ月連続のドル高レアル安となった。
(2)株式市場
(ア)8月のブラジルの株式相場(Bovespa指数)は、米国、中国、欧州の製造業関連の指標が改善したことを受け上昇して始まったが、米国の雇用統計が予想を下回ったこと等から下落し、6日に月内最安値となる47,422ポイントを記録。しかし、中国の貿易額や工業生産指数が好調だったこと、エジプト情勢の混乱を受け、原油などのコモディティ価格が上昇したこと、及び、為替相場でドル高レアル安が進行したことから輸出企業を中心とした株に買い注文が入ったことなどから株価は上昇。
(イ)その後、これまで上昇してきた株価に対する利益確定や為替相場での一時的なドル下落から、売り優勢の展開となったが、為替相場のドル高レアル安の傾向を受け、政府がガソリンなどの価格を引き上げることを発表したことから、ペトロブラス社の収益改善につながるとの見方が広まり、同社関連の株に買いが多く入ったこともあり、23日には月内最高値の52,197ポイントまで上昇した。
(ウ)しかし、シリア情勢の悪化と欧米諸国による軍事介入の可能性の高まりや、中銀がSelicを9.0%に引き上げたことから、株価は再び下落。月末には、発表された第2四半期GDPが市場予測より良かったこともあり若干値を戻し、前月末比3.68%のプラスとなる50.008ポイントで取引を終了した。
Copyright © 2012 - Embaixada do Japão - Todos os direitos reservados

