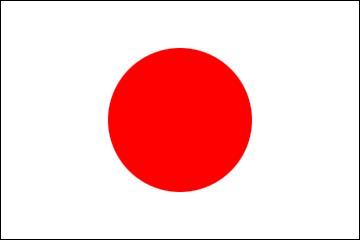最近の経済情勢 2015年9月
平成27年9月15日
(1)経済情勢等(8月発表の経済指標)
(ア)本年第2四半期のGDP成長率は、前期比マイナス1.9%、前年同期比マイナス2.6%となった。また、本年第1四半期のGDP成長率も、前期比マイナス0.2%から同マイナス0.7%に下方修正された。(イ)中銀が週次で発表しているエコノミスト等への調査に基づく経済成長予測に関し、8月28日時点では、本年の経済成長はマイナス2.26%で7週連続で下方修正、明年の経済成長はマイナス0.40%で4週連続で下方修正となった。一方で、本年のインフレ率見通しは9.28%でほぼ横ばいになった。
(ウ)7月の拡大消費者物価指数(IPCA)は単月で0.62%(前月比マイナス0.17%)、本年当初からの累計で6.83%、12か月累計で9.56%上昇し、本年当初からの累計でも政府のインフレ目標の上限である6.5%を上回った。
(エ)6月の鉱工業生産指数は、前年同月比マイナス3.2%で16か月連続のマイナス。また、7月の輸出額(米ドルベース)は前月比マイナス5.6%、輸入額は同6.9%のプラスで、5か月連続で貿易黒字を記録した。輸出品では、鉄鉱石の輸出額が前月比マイナス37.5%、原油が同マイナス61.5%と大幅に下落した。輸入品では、輸送機器の輸入額が前月比75.8%のプラスとなったのが目立った。
(オ)6月の小売売上高は、前年同月比マイナス2.7%となり、前月比でもマイナス0.4%で5か月連続のマイナスを記録。
(カ)国内主要6都市における7月の失業率は前月から0.6%上昇して7.5%となり、7か月連続で悪化。また、本年第2四半期の伯全土の失業率は8.3%であり、2012年以降で最悪の水準となった。
(2)経済政策等
(ア)政府は、自動車産業等の危機に瀕している経済セクターに対し、低金利の融資を供給するため公的銀行を再び活用することを決定した。これを受けて、8月18日にブラジル連邦貯蓄銀行(Caixa)は、従業員を解雇しないことを約束した企業に対し、低金利の融資枠を設けることを発表した。また、同19日にブラジル銀行(Banco do Brasil)は、低金利での融資を開始すると発表した。(イ)8月31日、政府は、2016~2019年度多年度計画法(PPA:伯予算の中期的目標を設定するもの)案及び2016年度年間予算法(LOA)案を議会に提出した。2016年度の基礎的財政収支はGDP比でマイナス0.34%とされ、従来の黒字目標である0.7%を大きく下回るものとなった。
(3)中銀の金融政策等
(ア)8月は政策金利(Selic)を決定する中銀の通貨政策委員会(Copom)は開催されていない。9月2日にCopomは、これまで7回連続して引上げられてきたSelicを14.25%に据え置く旨全会一致で決定した。(イ)8月6日、中銀は、為替市場への介入手段として実施している通貨スワップのロールオーバーを従来の水準からほぼ2倍に増やすと発表した。
(ウ)8月6日、中銀は、7月28・29日に開催したCopomの議事録を公表し、2016年末にインフレ率を目標の4.5%に収束させるシナリオは強化されているとの見解を示した。
(4)為替市場
(ア)8月のドル・レアル為替相場は、前月に引き続き、マクロ経済情勢の急速な悪化、政局の混乱及び中国の景気減速懸念の深刻化等を背景にリスクセンチメントが悪化し、大幅なドル高・レアル安が進行した。(イ)月の当初より、7月下旬に発表された基礎的財政収支の黒字目標の引下げと財政赤字の悪化が嫌気され、本年の最安値を更新する展開となった。上旬は各種経済指標の悪化や米国の早期利上げ観測を受けてレアル安が続き、5日には1ドル=3.5レアル台に入った。その後、6日に実施された中銀の為替介入により相場は一時的に落ち着き、1ドル=3.4レアル台で推移した。
(ウ)中旬に入ると、人民元の対ドル基準値の引下げが下落要因となった一方、米国の9月利上げ観測がやや後退したことが上昇要因となり、1ドル=3.5レアル前後で方向感なく推移した。
(エ)下旬に入り、上海株式市場の大幅な下落に端を発してリスクオフの動きが広がり、大幅なレアル安が進行した。政局の懸念等を背景に、25日には1ドル=3.6レアル台に突入した。その後、世界的な株価の回復により金融市場混乱の懸念が後退し、一時的に1ドル=3.5レアル台に戻ったものの、28日に本年第2四半期のGDP成長率が市場予想を超える下落となったこと等が嫌気され、再びレアル安の展開となった。月末は1ドル=3.6187レアルで取引を終えた(前月末比5.8%のレアル安・ドル高)。
(5)株式市場
(ア)8月のブラジルの株式相場(Ibovespa指数)は、前月に引き続き中国の景気減速懸念の深刻化等を背景に、大幅に下落する値動きとなった。(イ)上旬は、政局の混乱等が嫌気され、7日には50,000ポイントを割り込む大幅な下落を記録した。
(ウ)中旬に入り、人民元の基準値引下げを受けて中国の景気減速懸念が強まり、リスクオフの動きから株価は継続的に下落した。
(エ)下旬に入り、原油安や上海株式市場の急落等からグローバルに株価が全面安の展開となり、24日には一時42,000ポイント台を記録した。その後は、金融市場混乱の懸念が後退したこと等を材料に株価は一時上昇する場面もあったものの、第2四半期のGDP成長率が市場の予測を下回る数字になったことが嫌気され、再び株価は下落した。月末の株価は46,625ポイントとなり、前月末比8.3%の下落となった。