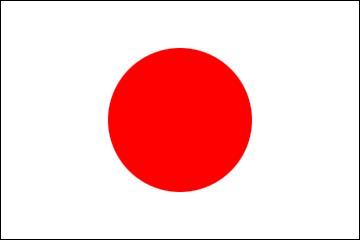第一回日伯学長会議の開催(1月31日)
令和7年2月11日
1月31日、筑波大学とサンパウロ大学の共催で、日伯友好交流年記念行事の一つとして、第一回日伯学長会議が開催されました。日本側、ブラジル側それぞれ10大学が参加し、日伯の学術交流史に残る記念すべき一日となりました。


筑波大学、東北大学、東京外国語大学、上智大学、創価大学、芝浦工業大学、福井県立大学、信州大学、島根大学、岡山大学。
(2) ブラジル側参加大学(計10大学)
サンパウロ州立大学(USP)、ABC連邦大学(UFABC)、ミナスジェライス連邦大学(UFMG)、リオ・グランジ・ド・スール連邦大学(UFRGS)、サン・カルロス連邦大学(UFSCAR)、サンパウロ連邦大学(UNIFESP)リオ・カトリック大学(PUC-RIO)、リオデジャネイロ州立大学(UERJ)、カンピーナス州立大学(UNICAMP)、ブラジリア連邦大学(UNB)。
(3) その他学術機関
ブラジル側:ブラジル高等教育支援・評価機関(CAPES)、国家科学技術開発審議会(CNPq)、サンパウロ州研究支援財団(FAPESP)
日本側:日本学術振興会(JSPS)、日本科学技術振興機構(JST)。
オープニングセッションには、林大使のほか、永田筑波大学学長、カルロッティ/サンパウロ大学(USP)学長、フイ・オッペルマンCAPES国際局長、ホドリゴ・パパ伯外務省サンパウロ代表事務所(ERESP)一等書記官、大根田修筑波大学国際室長、セルジオ・プロヴァストUSP国際関係部長が登壇し、日伯学長会議の開催に際し、祝辞を述べました。
さらに、カミーロ・サンターナ伯教育大臣及び藤原章夫文部科学省事務次官がビデオメッセージを寄せました。

林本使は挨拶の中で、発案から一年ほどで日伯学長会議を実現できたことについて、永田筑波大学学長、カルロッティUSP学長の尽力に謝意を述べたうえで、本会議が更なる学術分野における日伯協力の強固な礎となることを期待する旨を述べました。大使挨拶の全文はこちらをご覧ください。
カミーロ・サンターナ教育大臣は、ブラジルは世界最大の日系人コミュニティーを有し、日本には世界で5番目に大きいブラジル人コミュニティーが存在するという両国間の強い人的繋がりに触れたうえで、日伯の教育・研究機関が協力することで、未来を担う両国の若者のより良い人材育成に繋がることを期待する旨を述べました。
藤原章夫文部科学省事務次官は、昨年岸田総理(当時)が発表した、2033年までに40万人の外国人学生を日本へ受け入れる留学生計画に言及し、本会議を契機としたブラジル人留学生数の更なる増加に期待する旨を述べました。


(2)基調講演
二宮正人USP名誉教授が「Japanese Immigrants and their Education in Brazil」と題し、講演を実施しました。
(3)グループディスカッション
第1部では、「サイバーセキュリティ・AI」「海洋・災害対策」「気候変動・クリーンエネルギー」のテーマで3グループに分かれ、これらの複雑化するグローバル課題に、両国の高等教育機関はどう取り組むべきか、またどのような共同研究や大学間連携が可能か等の意見交換が実施されました。
第2部では、「コロナ禍以降の交換留学とオンライン教育」および「交換留学と語学学習(ポルトガル語と日本語の視点から)」をテーマに2グループに分かれ、意見交換が実施されました。
(4)日伯研究支援組織の紹介
CAPES及びCNPqがJSPS及びJSTとの共同プロジェクト実績を紹介しつつ、停滞している協力覚書の再締結や新たな共同研究プロジェクトの実現を望む意向が示されました。また、FAPESPが組織概要や研究支援スキームの説明を行いました。
日本側からは、JSPS及びJSTがビデオメッセージを寄せ、保有する研究支援スキームの概要、申請手順等の説明を行いました。
(5)共同宣言の署名
最終セッションでは、永田筑波大学学長とカルロッティUSP学長によって、共同宣言が採択されました。同宣言では、両国の大学が、(1)学術的連携の促進(2)学生交流の拡大 (3)グローバル課題解決への貢献 (4)持続的パートナーシップの構築、に取り組むことが約束され、日伯学長会議を一つのプラットフォームとして、今後も両国大学間の対話を継続し、日伯大学間の連携を強化していく意向が確認されました。


1 開催日時
1月31日(金)9:00~18:00(於:サンパウロ大学)2 参加機関
(1) 日本側参加大学(計10大学)筑波大学、東北大学、東京外国語大学、上智大学、創価大学、芝浦工業大学、福井県立大学、信州大学、島根大学、岡山大学。
(2) ブラジル側参加大学(計10大学)
サンパウロ州立大学(USP)、ABC連邦大学(UFABC)、ミナスジェライス連邦大学(UFMG)、リオ・グランジ・ド・スール連邦大学(UFRGS)、サン・カルロス連邦大学(UFSCAR)、サンパウロ連邦大学(UNIFESP)リオ・カトリック大学(PUC-RIO)、リオデジャネイロ州立大学(UERJ)、カンピーナス州立大学(UNICAMP)、ブラジリア連邦大学(UNB)。
(3) その他学術機関
ブラジル側:ブラジル高等教育支援・評価機関(CAPES)、国家科学技術開発審議会(CNPq)、サンパウロ州研究支援財団(FAPESP)
日本側:日本学術振興会(JSPS)、日本科学技術振興機構(JST)。
3 会議概要
(1) オープニングオープニングセッションには、林大使のほか、永田筑波大学学長、カルロッティ/サンパウロ大学(USP)学長、フイ・オッペルマンCAPES国際局長、ホドリゴ・パパ伯外務省サンパウロ代表事務所(ERESP)一等書記官、大根田修筑波大学国際室長、セルジオ・プロヴァストUSP国際関係部長が登壇し、日伯学長会議の開催に際し、祝辞を述べました。
さらに、カミーロ・サンターナ伯教育大臣及び藤原章夫文部科学省事務次官がビデオメッセージを寄せました。

カミーロ・サンターナ教育大臣は、ブラジルは世界最大の日系人コミュニティーを有し、日本には世界で5番目に大きいブラジル人コミュニティーが存在するという両国間の強い人的繋がりに触れたうえで、日伯の教育・研究機関が協力することで、未来を担う両国の若者のより良い人材育成に繋がることを期待する旨を述べました。
藤原章夫文部科学省事務次官は、昨年岸田総理(当時)が発表した、2033年までに40万人の外国人学生を日本へ受け入れる留学生計画に言及し、本会議を契機としたブラジル人留学生数の更なる増加に期待する旨を述べました。


二宮正人USP名誉教授が「Japanese Immigrants and their Education in Brazil」と題し、講演を実施しました。
(3)グループディスカッション
第1部では、「サイバーセキュリティ・AI」「海洋・災害対策」「気候変動・クリーンエネルギー」のテーマで3グループに分かれ、これらの複雑化するグローバル課題に、両国の高等教育機関はどう取り組むべきか、またどのような共同研究や大学間連携が可能か等の意見交換が実施されました。
第2部では、「コロナ禍以降の交換留学とオンライン教育」および「交換留学と語学学習(ポルトガル語と日本語の視点から)」をテーマに2グループに分かれ、意見交換が実施されました。
(4)日伯研究支援組織の紹介
CAPES及びCNPqがJSPS及びJSTとの共同プロジェクト実績を紹介しつつ、停滞している協力覚書の再締結や新たな共同研究プロジェクトの実現を望む意向が示されました。また、FAPESPが組織概要や研究支援スキームの説明を行いました。
日本側からは、JSPS及びJSTがビデオメッセージを寄せ、保有する研究支援スキームの概要、申請手順等の説明を行いました。
(5)共同宣言の署名
最終セッションでは、永田筑波大学学長とカルロッティUSP学長によって、共同宣言が採択されました。同宣言では、両国の大学が、(1)学術的連携の促進(2)学生交流の拡大 (3)グローバル課題解決への貢献 (4)持続的パートナーシップの構築、に取り組むことが約束され、日伯学長会議を一つのプラットフォームとして、今後も両国大学間の対話を継続し、日伯大学間の連携を強化していく意向が確認されました。