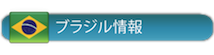
トピックス 2015年5月号
- 「“フィールドミュージアム構想”によるアマゾンの生物多様性保全プロジェクト」
- 内政
1.閣僚の交代
2.ブラジル全土で行われた大規模反政府デモ - 外交
1.伯ウクライナ宇宙開発協定の破棄の決定
2.伯米首脳会談
3.パク・クネ韓国大統領の訪伯
4.インドネシアにおけるブラジル人受刑者の死刑執行
「“フィールドミュージアム構想”によるアマゾンの生物多様性保全プロジェクト」
国立アマゾン研究所(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia: INPA)は,アマゾン熱帯地域の動植物・環境・生態学の研究を目的として1952年に設立されました。
近年は,その活動領域を広げ,アマゾンの熱帯地域の研究機関という役割に加え「市民の自然科学に対する興味や環境意識の向上」といった教育や,「科学技術開発とその活用」,「住民に興味及び憩いの場所の提供」というアマゾンの人々の環境整備や教育に重要な役割を担っています。
現在このINPAでは,京都大学と日本の様々な研究機関及びJICAが提携し,大規模プロジェクト「“フィールドミュージアム構想”によるアマゾンの生物多様性保全プロジェクト (ポルトガル語:Museu na Floresta)」が進められていますが,本記事ではそのプロジェクト概要等を紹介していきます。(以下執筆協力:JICA)
 INPA本部:マナウス 撮影者池田威秀
INPA本部:マナウス 撮影者池田威秀

- ポルトガル語プロジェクト名: Museu na Floresta
- 協力期間: 2014年7月22日~2019年7月21日(5年間)
- ブラジル側の実施機関: 国立アマゾン研究所(INPA)
- 日本側の実施機関: JICA、JST(科学技術振興機構)、京都大学(研究機関代表)、水産工学研究所、森林総合研究所、総合地球環境学研究所、須磨海浜水族園
- プロジェクトのHP
プロジェクトの意義
アマゾナス州の州都マナウスは、アマゾン川本流と支流ネグロ川の合流点に位置しアマゾンでも特に生物多様性に富んだ地域ですが、200万人近い人口と急速な都市の拡大により、貴重な自然環境が失われつつあります。この問題を解決するには、絶滅危惧種や生態系の研究・保全を進めると同時に、正確な情報にもとづいた環境教育を通じて都市住民の環境保全への理解・協力を得る必要があります。
近年、先進諸国では、一部の先進的な動植物園や水族館が、研究・保全・環境教育の拠点としての役割を担うようになってきましたが、アマゾンにはまだそのような動植物園や水族館は存在せず、環境保全に必要な生態研究も、研究技術や施設の制約により大きく遅れています。
本プロジェクトは日本とブラジルの共同研究活動を通じて、研究・環境教育・エコツーリズムの拠点を整備し、それらをネットワーク化して展示することで、アマゾンの生物多様性に関する正確な情報を地域住民に対して提供し、保全活動や環境教育、エコツーリズムに貢献することを目指しています。
プロジェクト概要
“フィールドミュージアム”とは、従来の博物館のような「箱もの」を飛び出し、各拠点をネットワーク化したものを展示する一連の活動と定義づけており、マナティやカワイルカなど、アマゾンの環境保全のシンボルとなっている野生動物の保護と環境教育を行います。
本プロジェクトは、ブラジル国内外からも注目を集めておりますが、より効果的にかつ継続的に事業を進めるためにも様々なステークホルダーとの協力が欠かせないため、企業からの支援(CSRなど)も大切なコンポーネントであると考えています。
観光分野においては、将来マナウスの観光ツアーの一候補として、日本が支援した本プロジェクトの現場への訪問も視野に入れ、研究の拠点に留まらないマナウス市に加え、クイエイラス川周辺の熱帯雨林プロジェクト等も活動サイト等、アマゾンの貴重な生態系を体験できるエコツーリズムも試行予定です。
また、INPAでは複数のマナティが保護されており、野生復帰に向けて準備が進められておりますが、同プロジェクトではアマゾンマナティなどの絶滅の危機にさらされている野生動物を飼育、半飼育(半野生)、野生下で観察・研究できる施設と保護区の整備を進めております。
 撮影者 山本友紀子
撮影者 山本友紀子
プロジェクトの様子
 水面から鼻を出すマナティ。アマゾン川の水は濁っているため、このように至近距離でも生物の直接観察は難しい。最新の技術・機材によって生態系を明らかにすることがプロジェクトの目標の一つ。(撮影者 菊池夢美)
水面から鼻を出すマナティ。アマゾン川の水は濁っているため、このように至近距離でも生物の直接観察は難しい。最新の技術・機材によって生態系を明らかにすることがプロジェクトの目標の一つ。(撮影者 菊池夢美)
 もう一つのプロジェクト活動サイトであるクイエイラス川周辺の熱帯雨林。研究の拠点となるだけでなく、アマゾンの貴重な生態系を体験できるエコツーリズムも試行予定。(撮影者 池田威秀)
もう一つのプロジェクト活動サイトであるクイエイラス川周辺の熱帯雨林。研究の拠点となるだけでなく、アマゾンの貴重な生態系を体験できるエコツーリズムも試行予定。(撮影者 池田威秀)
 絶滅が危惧されているアマゾンカワイルカの音声を記録し、分布や行動を調査している。これらのデータは保護活動に活かされる。(撮影者 矢部恒晶)
絶滅が危惧されているアマゾンカワイルカの音声を記録し、分布や行動を調査している。これらのデータは保護活動に活かされる。(撮影者 矢部恒晶)
プロジェクトの目標、期待される成果、活動
活動を通じて得られる成果①: 対象地域の代表的生物・生態系の研究・保全が最新の技術・手法によって促進される。
活動内容①: 水生哺乳類(マナティー、カワイルカ)、魚類、森林生態系について、調査研究を行い、アマゾンの生物多様性・生態系の実態を解明する。
活動を通じて得られる成果②: フィールドミュージアムのコンポーネント(施設および展示)が構築・ネットワーク化される。 活動内容②: 生物および森林生態系の研究・展示のための施設を整備する。また、これらの施設と、既存の保護区や環境教育施設との連携を進める。
活動を通じて得られる成果③: フィールドミュージアムの運営プログラム及びマネジメントシステムが構築される
活動内容③: フィールドミュージアムが持続的に運営されるよう、ステークホルダーを組織化する。またステークホルダーと連携して、環境教育やエコツアーのプログラムを構築する。
内政
1.閣僚の交代
(1)4月7,伯大統領府は,ヴァルガス大統領府政治調整担当庁長官の職を辞任し,テメル副大統領がこれを兼任すること発表した。なお,報道によれば,大統領府政治調整担当庁長官の交替は,昨今一連の政府とPMDBとの関係悪化に鑑み,PMDBや一部のPT議員,そしてルーラ前大統領がルセーフ大統領に対して,ヴァルガス政治調整担当長官を交替させるべきとの圧力をかけたことから,交渉が始まったものとされている。
(2)4月8日,伯大統領府はサルヴァッティ大統領府人権庁長官が辞任し,ヴァルガス前大統領府政治調整担当庁長官が後任となる旨発表した。
(3)4月15日,伯大統領府は,ラジェス観光大臣が辞任し,エンリッケ・エドゥアルド・アルヴェス前下院議員(前下院議長)が後任となる旨発表した。
2.ブラジル全土で行われた大規模反政府デモ
(1)4月12日,反政府デモが25の州及び連邦区の約200都市において行われ,約70万人(警察発表)が参加したが,先月15日のデモ(約170万人)と比べれば,動員数は半分以下となった。なお,今回のデモは,終始,平和的に行われ,警官隊との衝突,略奪等の混乱は見られなかった。
(2)主要都市に於ける参加者数及び前回との比較は以下の通り。サンパウロ:27.5万人(前回:100万人),リオデジャネイロ:2万人(10万人),ブラジリア:2.5万人(4.5万人),ベロオリゾンテ:5千人(2.6万人),ポルトアレグレ:3.5万人(10万人),サルヴァドール:2千人(1.2万人),レシフェ:8千人(5千人),マナウス2.3千人(1.3万人)。
(3)今回のデモが前回と比べて下火となったのは,前回のデモは4か月以上前からデモが告知されていたが,今回の告知期間が短く,また前回デモから一ヶ月も経たないうちに行われたことによるタイミングの問題が原因ではないかと見られている。また,サルヴァドール,ベレン,マナウス等では雨天が原因とされている。
(4)デモの参加者の主要な主張は,反ルセーフ大統領,反政府,反PT,反汚職等であった。少数派ではあるが,軍事政権の復活を求めるグループが今回のデモにおいても出現し,注目を集めた。
(5)フォーリャ・デ・サンパウロ紙の分析記事は以下のとおり。
今回のデモにより,反政府運動が下火となったと見るのか,または未だにこれだけのデモ隊を動員できるだけの勢いを持っていると見るのかで意見が分かれるところであるが,デモの参加者が前回から減ったとは言え,今回も相当な規模のデモが発生したと見るべきである。政府からしてみれば,一息つけたということなのであろうが,最新の世論調査によれば,国民の63%がルセーフ大統領の弾劾を支持しており,危機から脱したとは言い難い。
外政
1.伯ウクライナ宇宙開発協定の破棄の決定
(1)ルセーフ大統領は,関係省庁が作成した報告書を受け,伯ウクライナ宇宙開発協定の破棄を決定した。右協定の破棄は,本年1月,同大統領と関係閣僚(国防,科学技術,外務各大臣及び文官長)の会議で決定されたが,ウクライナ政府には通報されていないので,同協定は未だ効力を有している。
(2)協定破棄の理由は,伯の財政難により,サイクロン4型衛星打ち上げロケットの非常に高いコストに対応できなくなったことにある。伯ウクライナ両国は,協定の締結(2003年)から約12年間に亘り,商業衛星をサイクロン4型ロケットにより伯のアルカンタラ基地から打ち上げるとの計画に約10億レアルを投資してきたが,未だに打ち上げは行われていない。両国は,2006年に「アルカンタラ・サイクロン・スペース社」を設立し,2010年に打ち上げを行う予定であったが,資金難並びに先住民との間で土地の所有権を巡る争いが発生したため,打ち上げは2015年に延期されたが,今のところ,打ち上げ基地の施設は半分ほどしか完成していない。ウクライナが2014年から内戦状態にあることも,同国に対する不信感を募らせる要因となっている。
(3)ウクライナとの協定が破棄されれば,対米交渉への道が開けることになる。米国は,アルカンタラ基地の商業利用に強い関心を有している。伯米両国は,2000年に米国が同基地を使用することで合意したが,米国が技術の共有を拒んだため,実現には至らなかった。ルセーフ大統領は,米国情報機関の盗聴事件により冷え込んだ米国との関係を修復しようとしており,同基地の使用が再び俎上に上る可能性がある。また,ロシアは,以前から,伯に対し,ウクライナとの協定を破棄するよう働きかけていたところ,ロシアが伯に衛星打ち上げロケットを提供する可能性がある。
2.伯米首脳会談
(1)4月11日、パナマで開催された米州首脳会議と並行して、ルセーフ大統領はオバマ大統領との首脳会談を行い、本年6月30日に米国を実務訪問することで合意した。会談において、両首脳は科学技術、イノベーション及び防衛分野における協力,民間航空,米州における民主主義の構築,気候変動及び代替エネルギーについて意見交換を行なっている。
(2)ルセーフ大統領は、国賓訪問ではなく,実務訪問を選択したことに関し,「国賓として訪問するのであれば明年にせざるを得ないが、それでは米国の大統領選挙と重なることとなる。そのため、我々は本年6月末に訪米を行うこととした。」と述べた。
(3)オバマ米大統領は、「ルセーフ大統領が6月にワシントンを訪問することになり、非常に満足している。その際、我々は気候変動、エネルギー、教育、科学技術等のテーマについて話し合いを行う予定である。また、議論を深めるだけでなく、協力に関する具体的なプランを作ることが出来るであろう。」と述べている。また、伯米関係を揺るがしたNSAによる盗聴事件に関し、「米国政府は、伯だけではなく全ての友好国に対し、スパイ行為の対象とはならないことを伝えている。」と述べた。これに対しルセーフ大統領は、「オバマ大統領が何かについて知りたければ、自分(ルセーフ大統領)に電話する。」と補足した。
3.パク・クネ韓国大統領の訪伯
(1)4月24日、ルセーフ大統領は、パク・クネ大統領と首脳会談を実施し,両首脳は貿易及び投資を中心に二国間及びグローバルなアジェンダにおける諸課題を議論したほか、両国間の協力の深化等について話し合った。首脳会談後には、成果文書への署名式が行われ、両国首脳、関係閣僚及び企業トップが、教育、租税、エネルギー、保健、情報技術の分野における成果文書に署名した。
(2)ルセーフ大統領は、より高い付加価値の品目の対韓国輸出などを通じ,両国間貿易の品目を多様化させるべく努力する余地があるとした上で,貿易円滑化及び中小企業間取引促進に係わる2つの合意によりこれを後押ししていく旨発言し,サンタカタリーナ産生鮮豚肉の韓国輸入解禁を繰り返し要請した。
(3)ルセーフ大統領は、パク・クネ大統領の朝鮮半島の平和・安定のための努力を讃えた上で、双方の2016-2018年、2017-2019年の人権理事会理事国立候補に係わる相互支持で一致した旨発言。また,伯は韓国・北朝鮮の両方と外交関係を有する国として、六者協議の早期再開を求めるとともに,地域の和平プロセスや人権擁護のために協力する用意がある旨表明した。
(4)両国のアジェンダは科学技術協力・学術交流といった分野にも広がっている。2012年以降,韓国の大学は,「国境無き科学計画」を通じ525人の伯人留学生(アジアでは最大)を受け入れている。
4.インドネシアにおけるブラジル人受刑者の死刑執行
(1)4月28日,インドネシアで伯人男性1名を含む8名の銃殺刑が執行された。伯政府は,インドネシアに対する措置の検討を発表するとともに,世界的な死刑のモラトリアムを主張するとしている。
(2)ダネーゼ外務次官は,「(伯人男性の死刑執行は)二国間関係にとり深刻な事態である。二国間貿易は50億米ドルに達し,伯の黒字となっているが,大統領が何度も働きかけを行ったにも拘らずインドネシア政府から満足の行く回答が得られなかったことは,検討に値するものである。大切なのは,同国との対話を試みることである。その次に,両国がこの問題の克服方法について検討する必要がある。我々は,死刑を適用している国々が死刑を漸次廃止するよう,説得するための取組に努力を傾注している。一つの方法としては,死刑のモラトリアムが考えられる。」と述べている。
(3)両国関係は,既に儀礼的なものとなっている。本年1月17日に最初の伯人死刑囚が処刑された後,ルセーフ大統領は駐インドネシア伯大使を呼び戻した。同大使はそのまま離任となったが,後任の大使は未だ任命されていない。本年2月,ルセーフ大統領はリヤント駐伯インドネシア大使の信任状奉呈を拒否し,同大使は帰国しなければならなかった。
(4)今回処刑された死刑囚は,2004年にコカイン6キロをインドネシアに密輸しようとして空港で逮捕され,翌年に死刑を宣告され,家族及び伯政府による控訴,助命嘆願等の働きかけは全て失敗に終わっている。今回処刑された伯人男性は,平時に海外で処刑された伯人としては,同じく本年1月にインドネシアで麻薬密輸の罪により処刑された男性に続き,2人目である。
Copyright © 2012 - Embaixada do Japão - Todos os direitos reservados

